自分に合ったトレーニングメニューを確立すること。
それは筋トレに励む人にとっての永遠のテーマであり、ボディメイクにおいて重要な要素のひとつです。
だからこそ、今まさに筋トレを始めたばかりの方や、成長に停滞を感じているという方は、トレーニングの組み方に対する知識を深める必要があります。
そこで、本記事では1週間の部位のローテーションから、セット数、種目の詳細にいたるまでを分割法を中心に解説!
筋肥大にとって効果的なトレーニングメニューを、初心者の方にもわかりやすく紹介していきます。
筋肉の部位の種類とは!?
まず、筋肉の部位は大きく5つに分けられます。
胸(上部、中部、下部)
背中(広背筋、僧帽筋、脊柱起立筋)
脚→(大腿四頭筋、ハムストリング)
腕(上腕二頭筋、上腕三頭筋)
肩→(三角筋)
これらの部位を2、3日に分けて行うのか、それとも1週間かけてじっくり行うのかは、それぞれの生活スタイルや体質などによって変わってきます。
それでは、各部位を分けてトレーニングする”分割法”について見ていきましょう。
分割法のメリット・デメリット

メリット
分割法の最大のメリットは、短時間で1つの部位に強い負荷をかけられることです。
全身法だと、どうしても1回のトレーニング時間が長くなることや、それぞれの部位への刺激が減ってしまうことが懸念されます。
例えば、平日の仕事終わりにトレーニングをして、休日は自分の趣味などに時間を使いたいという方には分割法が合っているといえるでしょう。
また、全身を鍛えるよりは1回のトレーニングの疲労度も軽減されるので、集中力を維持してトレーニングができるというメリットもあります。
デメリット
デメリットとしては、筋トレをする日数が増えてしまうことや、1つの部位を扱う頻度が減ってしまうことが挙げられます。
日数の増加に関しては、人それぞれの生活スタイルや好みの問題もあるため、休日を使って一気にトレーニングがしたいのであれば全身法をおすすめします。
扱う部位の頻度については、たしかに全身法よりも回数は減ってしまいます。
ただ、分割の方法によっては特定の部位を週2回にすることは可能ですし、そもそも、分割法は1回のトレーニングの刺激が強いというメリットもあります。
そのため、週に1回のペースで同じ部位を鍛えられるのであれば、頻度についてそこまで気にする必要はないでしょう。
分割法における部位の組み合わせ
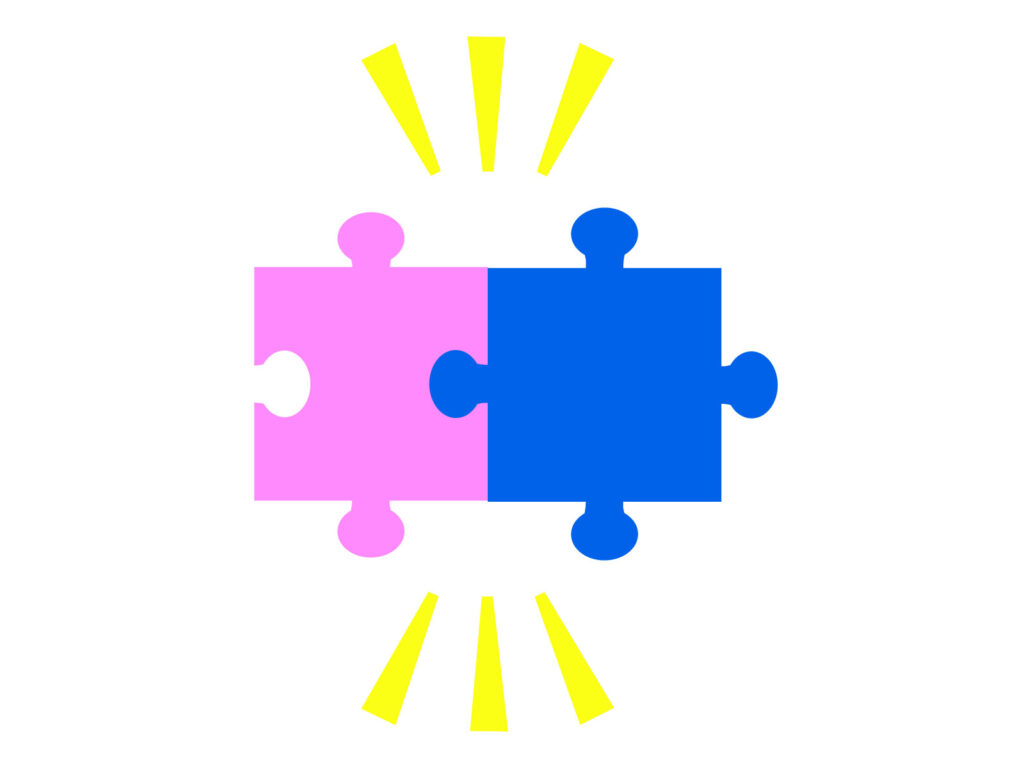
先ほども述べたように、分割法にはジムに通う日数が多くなるというデメリットがあります。
つまり、主要部位をそれぞれ1日ずつ鍛えていたら、少なくとも週5日はジムに通わなくてはいけません。
週5日も筋トレに費やすのは、仕事や家事で忙しい方にとってあまり現実的ではありませんし、体力的にもすぐに限界が来てしまうでしょう。
そこで大切になってくるのが、部位を組み合わせてトレーニングをするということです。
例えば、胸の日に上腕三頭筋も一緒に鍛えるといった形で、相性のいい部位をまとめてしまうという方法があります。
ただ、まとめる部位の相性は人によって考え方が異なるため、一概に「この部位とあの部位を同じ日にやれ!」とは断言できません。
そこで、ここからは部位をまとめるうえで参考となる考え方について、3つ紹介します。
主動筋×補助筋
トレーニング動作において中心的な役割を担う”主働筋”と、それを支える“補助筋”を同じ日に鍛える方法。
胸 上腕三頭筋
背中 上腕二頭筋
肩(ショルダープレス) 上腕三頭筋
補助筋は、必ず主働筋の後に鍛えるようにしましょう。
もし補助筋を先に鍛えてしまうと、主働筋を鍛える際に力を発揮でなくなってしまいます。
同じ日に鍛えるメリットは、主動筋を先に鍛えることで補助筋も温まるため、スムーズに2つの部位を鍛えることができるという点です。
入念な準備運動ができている状態に近いため、関節などのケガ防止に繋がることに加え、低重量でも追い込めるというメリットがあります。
反対にデメリットとしては、補助筋を鍛える際に高重量が扱いにくいということです。
主働筋を先に鍛えるわけですから、当然、補助筋は通常よりも疲弊しています。
そのため、フレッシュな状態でトレーニングするよりも重量が落ちてしまうことは避けられません。
前述のように低重量でも筋肉を追い込むことは可能ですが、効きづらさや成長の停滞を感じる場合には、部位の組み合わせを見直すように心がけましょう。
拮抗筋
メインとして鍛えている部位に対して反対の動きをする筋肉、“拮抗筋“を同じ日に鍛える方法。
胸=背中
上腕二頭筋=上腕三頭筋
大腿四頭筋=ハムストリング
拮抗筋を同じ日に鍛えるメリットとしては、インターバル時間を短くできる点が挙げられます。
というのも、メインとして動く主働筋を鍛えている間、拮抗筋は完全に脱力状態にあります。そのため、前半に主働筋を鍛えた後、すぐに拮抗筋を鍛えることも可能ですし、主働筋と拮抗筋で交互にセットを組むこともできます。
時間の効率という面では、非常に大きな利点ですね。
また、拮抗筋はメインとして鍛えている主働筋のほぼ反対側に位置しているため、どちらも意識しながら鍛えることで、よりバランスのいい身体になります。
拮抗筋同士の相乗効果も期待できるため、通常よりもパンプアップさせられる可能性も秘めています。
デメリットは、胸と背中を行う日ができてしまい、体力的な負担が大きくなってしまう点です。
どちらも大きい筋肉であるため、それなりに負荷のかかるメニューを多くこなすことになります。つまり、必然的に体力の消耗も激しくなり、全体的な重量のボリュームも落としかねません。
筋肉にとって大切なのは、常に新しい刺激を更新し続けることです。
大きい筋肉を同じ日に行うことで重量が伸び悩むのであれば、違う方法も試してみましょう。
プッシュ・プル
プッシュ(押す動作)とプル(引く動作)で分ける方法。
2分割する際に有効な方法で、プッシュの日にはプレス系の種目を、プルの日には引っ張る系の種目を行います。
〇プッシュ系の部位
胸、肩、上腕三頭筋、大腿四頭筋
・種目例
ベンチプレス
インクラインダンベルプレス
ショルダープレス
サイドレイズ
スクワット
レッグプレス
ナローベンチプレス
フレンチプレス
〇プル系の部位
背中、上腕二頭筋、ハムストリング
・種目例
ラットプルダウン
デッドリフト
ローイング
アームカール
ハンマーカール
インクラインアームカール
レッグカール
プッシュ・プル法のメリットは、初心者でも取り組みやすい点と、2日ほどで全身を満遍なく鍛えることができる点です。日々忙しい方や、筋トレの習慣を身に付けたいという方には向いているでしょう。
デメリットとしては、ひとつの部位に対する種目数が減ってしまうことが挙げられます。
例えばプレス系の日だと、胸、脚、肩、三頭を行うため、必然的に各部位は2種目ほどになってしまいます。
もし種目数の減少を防ぎたいのであれば、プッシュA、プッシュB、プルA、プルBといった形で、プッシュプルの中でもそれぞれ2つに分けて、週に4回ほどで行うことを検討してみましょう。
また、下半身は別の日に行うなど、工夫次第で1日にあたりの負担を軽減することができます。
分割法を行う上での注意点
分割法を行う上で大切なのは、回復時間を考慮することです。
先ほども述べたように、メインとして鍛える筋肉には、それを支える補助筋が存在します。
つまり、補助筋をメインとして鍛える場合は、補助として使った日から間隔を空けないと、疲労がたまった状態でトレーニングを行うことになってしまいます。
逆も然りで、補助筋をメインで鍛えた次の日に、補助される主働筋を鍛えるのもよくありません。
補助筋が疲労していると、主導筋を支える際に力が発揮しきれませんからね。
例えば、胸の日と上腕三頭筋の日を近づけるのはNGです。
三頭筋の回復には48時間ほど要するので、少なくともそれくらいの期間は間隔を空けるように心がけましょう。
それぞれの筋肉の対応関係を理解し、適切な回復時間を設けることが分割法のトレーニングにとって大切です。
おすすめ分割スケジュール
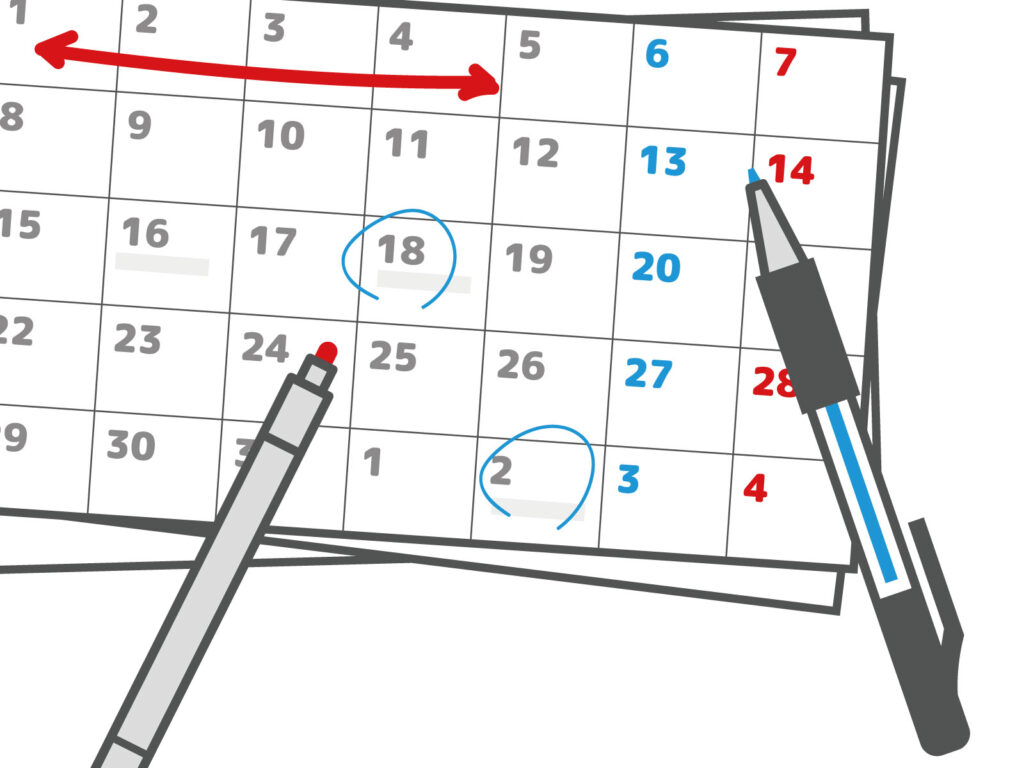
ここからは、本サイトのおすすめ分割スケジュールを紹介します。
これまで解説した分割法における考え方も踏まえつつ、初心者の方々を主な対象とした、取り組みやすい内容を重視しました。
セット数やレップ数についても詳しく記載しておりますが、その根拠については次の章で詳しく解説しております。
また、重量としては、8~12回くらいで限界が来る重さで設定しましょう。
2分割
胸、肩、大腿四頭筋、(三頭)の日(プッシュ系)
・ベンチプレス ※三頭を補助筋として使用
8~12回 3セット
・ダンベルフライorペックフライ
8~12回 3セット
・ショルダープレス ※三頭を補助筋として使用
8~12回 3セット
・スクワット
8~12回 3セット
(・フレンチプレス
8~12回 2~3セット)→三頭は補助筋として使っているため余裕があれば行う
背中、二頭、大腿二頭筋の日(プル系)
・ラットプルダウン
8~12回 3セット
・デッドリフト(脚も使える)
8~12回 3セット
・レッグエクステンション
8~12回 3セット
・バーベルカール
8~12回 3セット
(・インクラインアームカール
8~12回 2~3セット)→余裕があれば行う
トレーニングの間隔としては、プッシュ系から3日間空けてプル系を行うようにしましょう。
とくに脚に関しては、どちらも日にも種目が入っているため、連続してトレーニングすると疲労が抜けない可能性があります。
3分割
胸、三頭の日
・ベンチプレス
8~12回 3セット
・インクラインチェストプレス ※大胸筋上部狙い
(スミスマシンかダンベルでも代用可能)
8~12回 3セット
・ペックフライorダンベルフライ
8~12回 3セット
・フレンチプレス
8~12回 2~3セット
・スカルクラッシャー
8~12回 2~3セット
背中、二頭の日
・ラットプルダウン
8~12回 3セット
・ベントオーバーロー
8~12回 3セット
・プーリーロー
8~12回 3セット
・バーベルカール
8~12回 2~3セット
・インクラインアームカール
8~12回 2~3セット
脚、肩の日
・スクワット
8~12回 3セット
・レッグエクステンション
8~12回 3セット
・レッグカール
8~12回 2~3セット
・ショルダープレス
8~12回 3セット
・サイドレイズ
8~12回 2~3セット
胸の日に肩のトレーニングを行っても相性的には問題ありませんが、3つの部位を同じ日に鍛えるのは体力的に難しいと判断し、脚の日に回しました。
ただ、人それぞれ好みはあると思いますので、脚の日は脚だけに集中したいという方は、胸の日に肩をくっ付けても問題ありません。
4分割
胸の日
・ベンチプレス
8~12回 3セット
・インクラインチェストプレス ※大胸筋上部狙い
8~12回 3セット
・ディップス ※大胸筋下部狙い
8~12回 3セット
・ペックフライorダンベルフライ
8~12回 3セット
・(ダンベルプルオーバー
8~12回 2~3セット)余裕があれば行う
背中、二頭の日
3分割の「背中、二頭」の日と一緒
肩、三頭の日
・ショルダープレス
8~12回 3セット
・サイドレイズ
8~12回 3セット
・フレンチプレス
8~12回 3セット
・スカルクラッシャー
8~12回 3セット
脚の日
・スクワット
8~12回 3セット
・シーテッドレッグプレスorハックスクワット
8~12回 3セット
・レッグエクステンション
8~12回 3セット
・レッグカール
8~12回 3セット
5分割
胸の日
4分割の「胸」の日と一緒
背中の日
・ラットプルダウン
8~12回 3セット
・デッドリフト
8~12回 3セット
・ベントオーバーロー
8~12回 3セット
・プーリーロー
8~12回 3セット
肩の日
・ショルダープレス
8~12回 3セット
・アーノルドプレス
8~12回 3セット
・サイドレイズ
8~12回 3セット
・リアデルト
8~12回 3セット
二頭、三頭の日
・バーベルカール
8~12回 3セット
・インクラインアームカール
8~12回 3セット
・フレンチプレス
8~12回 3セット
・スカルクラッシャー
8~12回 3セット
脚の日
4分割の「脚」の日と一緒
適切なセット数・レップ数とは?
筋トレの理想的なセット数としては、1種目につき3~4セットが適切です。
仮に2分割で筋トレをしているとしたら、各種目3セットの方が体力的には丁度いいでしょう。反対に、分割の回数が多くなればなるほど、セット数は増やしやすくなります。
先ほど紹介したメニューの中には、2~3セットと記載した種目もいくつかありましたが、体力的に余裕があるのであれば3セット行うことをお勧めします。
また、メインとなるセットを行う前には、必ず軽い重量でウォームアップセットを行うようにしましょう。
重量としては10~12レップほどで限界に達すように設定し、インターバルは1~2分程度を心がけると、筋肥大には有効です。
ちなみに、筋持久力を上げることが目的の場合、比較的軽い重量で2~30回程度反復運動をし、インターバルも短めに設定することが効果的とされています。
特定のスポーツ技能の向上や、ダイエットをメインとしている方などに向いているトレーニング方法ですね。
筋トレの目的が変われば、重量やインターバルの長さも対応して変化するということが、お分かりいただけるでしょう。
まとめ
本記事では、トレーニングメニューの組み方について、分割法を中心に解説しました。
分割法にもさまざまな種類があり、自分に合った方法を選ぶことが大切出ることが大切です。
みなさんも、本記事やその他の筋トレ情報を参考に、自分の生活スタイルや目標とする体型に合ったトレーニングスケジュールを組んでいきましょう!
I am Traineeでは、その他にも筋トレに関するお役立ち情報を公開中!
https://iam-trainee-blog.com/ 詳しくはこちらのURLをクリック!
また、本サイトでは、ジム情報や筋トレに特化したSNSも公開中ですので、そちらの方も是非チェックしてみてください!




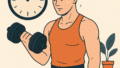
コメント